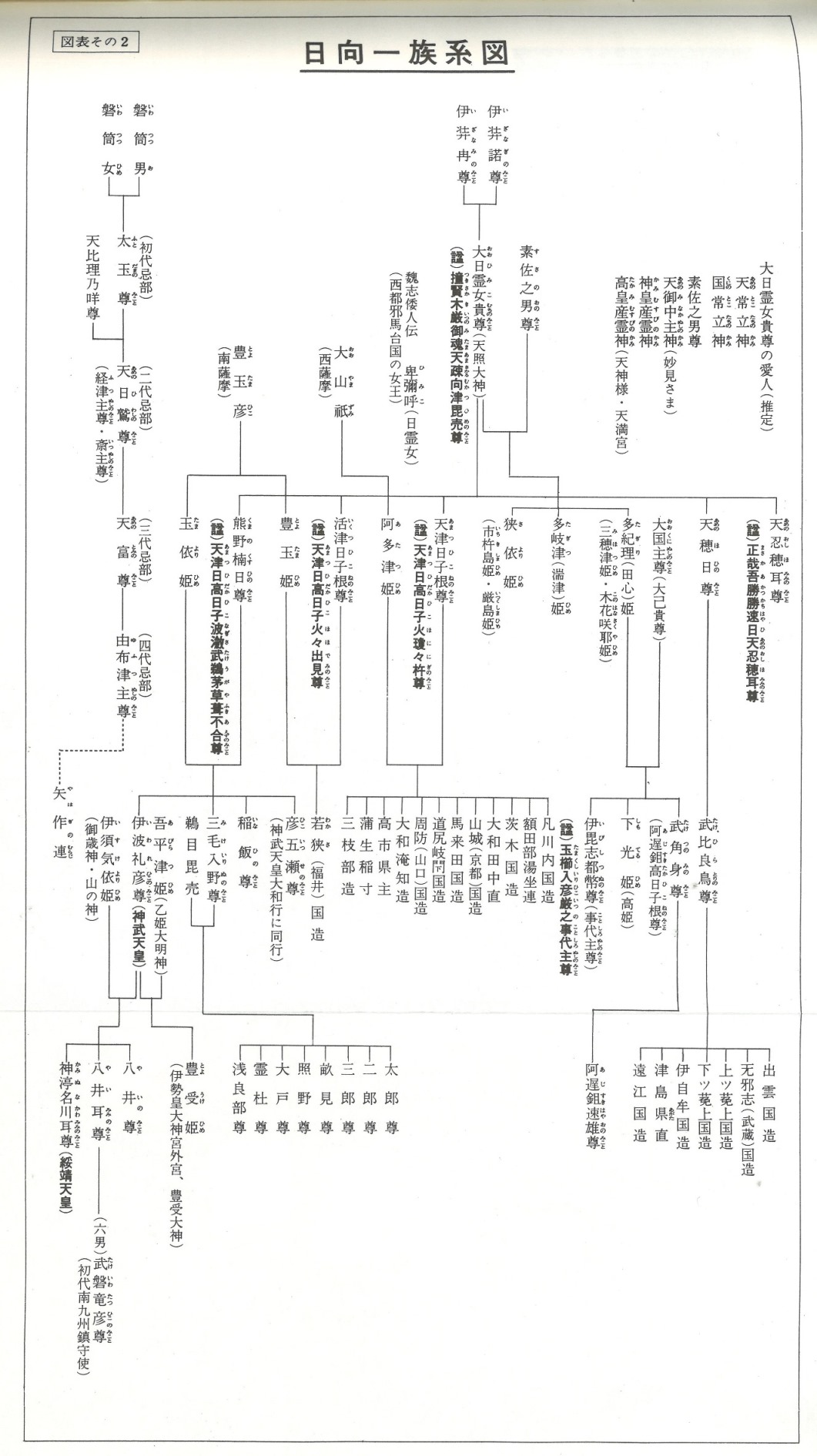中腹からの景色
中腹からの景色
 他にも、和歌山の有田市には八王子公園があり、除虫菊の記念石碑が建てられています。僕が子供の頃
には、鬼ごっこをしたり、傍を走る汽車の窓に向かって、どんぐりの実をパチンコで打ち込んだりして
遊んだものでしたが、桜の大木がたくさん植えられた思い出の場所となっています。
その一角には鳥居があって、普段は誰も立ち入ることはありませんが、小さな石社が祀られています。
母親の話では、昭和28年に有田川の洪水があって堤防が出来るまでは、今の3倍くらい広くて、夏祭り
では屋台が立ち並ぶほど賑やかな場所になっていたそうです。
関西にある八王子神社に祀られているのは、出雲で素佐之男(スサノオ)と奇稲田姫(クシイナダヒメ)
との間に生まれた八人の子供です。
八島野(ヤシマヌ)、五十猛(イタケル)、大屋津姫(オオヤツヒメ)、抓津姫(ツマツヒメ)、
饒速日(ニギハヤヒ)、宇迦御魂(ウガノミタマ)、磐坂彦(イワサカヒコ)、須世理姫(スセリヒメ)
は京都の八坂神社にも祀られています。
ヤマタノオロチからクシイナダヒメを取り戻した後に、スサノオが詠んだ、日本最古の和歌がこちら、
八雲立つ 出雲八重垣 妻ごめに 八重垣つくる その八重垣を
古代日本正史で原田常治氏が紹介しているけど、八の字に込められた思いは。。。と想像が尽きないね!
他にも、和歌山の有田市には八王子公園があり、除虫菊の記念石碑が建てられています。僕が子供の頃
には、鬼ごっこをしたり、傍を走る汽車の窓に向かって、どんぐりの実をパチンコで打ち込んだりして
遊んだものでしたが、桜の大木がたくさん植えられた思い出の場所となっています。
その一角には鳥居があって、普段は誰も立ち入ることはありませんが、小さな石社が祀られています。
母親の話では、昭和28年に有田川の洪水があって堤防が出来るまでは、今の3倍くらい広くて、夏祭り
では屋台が立ち並ぶほど賑やかな場所になっていたそうです。
関西にある八王子神社に祀られているのは、出雲で素佐之男(スサノオ)と奇稲田姫(クシイナダヒメ)
との間に生まれた八人の子供です。
八島野(ヤシマヌ)、五十猛(イタケル)、大屋津姫(オオヤツヒメ)、抓津姫(ツマツヒメ)、
饒速日(ニギハヤヒ)、宇迦御魂(ウガノミタマ)、磐坂彦(イワサカヒコ)、須世理姫(スセリヒメ)
は京都の八坂神社にも祀られています。
ヤマタノオロチからクシイナダヒメを取り戻した後に、スサノオが詠んだ、日本最古の和歌がこちら、
八雲立つ 出雲八重垣 妻ごめに 八重垣つくる その八重垣を
古代日本正史で原田常治氏が紹介しているけど、八の字に込められた思いは。。。と想像が尽きないね!